Nikon歴代のAFサンニッパ ― 2014年10月02日 23時29分
次望遠レンズを買うとしたら何が良いか。
現状のAF-S 70-200mm f/2.8G ED VRIIにテレコンという体制から、将来的にもう少し焦点距離の長いレンズを追加したい、という考えから、まず浮かんだのが以下の案。
・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
・SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports
80-400mmは、Nikonを代表する動きモノ撮影に欠かせない望遠ズームレンズ。
初代80-400mmは、NikonのFマウントレンズ初のVRを搭載したレンズとして長く君臨、現行の二代目は、待望のAF-S化を果たしたレンズで人気。
画質も、70-200mmにテレコンを使うより良好とのことで、純正レンズでもあり信頼性も高く、候補の筆頭でした。
ただ、70-200mmと焦点距離がかぶるのが気になります。
SIGMAの150-600mmは、焦点距離が長いので、これを1本追加すれば、満足度は高そうです。最近のSIGMAは、純正に勝るとも劣らない画質で、現時点ではまだ発売されていませんが、期待できそうです。
純正レンズではないので、歪み補正は使えませんが、用途的に歪みが気になることもないとは思います。
ただ、信頼性や耐久性の面では、やはり純正に分があるでしょう。
ズームレンズ、近年は画質が向上したものの、やはり望遠域は単焦点レンズの並外れた解像力と画質も魅力。ズームレンズを買っても、望遠端での使用が多い、となると、画質に長けた単焦点レンズの方が良いのでは、と思うように。
実際、ズーミングしながらの撮影は、フレーミングがおろそかになりがち。単焦点であれば、フレーミングに集中できるのでは、ということから、サンニッパかサンヨンを導入した方が良いのでは?
ただ、サンヨンのほうは、現行品はVRのない少し古い設計で、これはVR化を待ちたいところ。画質は古いけど非常によいとの評価。
一方、サンニッパは、やはりプロやハイアマチュアの定番望遠単焦点レンズだからか、数年毎にモデルチェンジされて改良されています。つまり、中古を含めると、選択肢は非常に多いです。
ということで、今後の選択の為の記録として、ここいらで唐突に、AF化されて以降のNikonの歴代サンニッパをまとめてみました。
●Ai AF Nikkor 300mm F2.8S IF-ED(1986)
AFが初めて搭載されたF501や同期に発売されたレンズ。
光学系は、1977年に発売されたAiレンズと同等。
ボディ内蔵モータによるAFとなる。このレンズは実家にあり、使ったことがありますが、さすがにAFは速くはないですが、遅すぎて困るという印象でもない。
ただし、当初からレンズ内蔵AFモータを採用したCanonよりは遅く、これを機にCanonへ移行したスポーツカメラマンが多かったとのこと。
古いレンズですが、画質はなかなかどうして悪くなく、現代でも十分通用します。ズームレンズとは一味じがったワンランク上の描写が楽しめます。
三脚使用前提で、AFをそれほど重視しないなら、このレンズでも十分。
中古価格は概ね10万円台半ば。古いので、タマ数は少なくなりつつあります。
ちょうど、D300で撮影した作例がありますので、掲載しておきます。
●Ai AF Nikkor 300mm F2.8S IF-ED(New)(1988)
F4と同時期に発売されたレンズで、上記レンズのA-M切り替えリングのデザインが変更されたもの。
外装デザイン以外は、前のレンズと同じ。
こちらも中古価格は概ね10万円台半ば。やはり古いので、タマ数は少なくなりつつあります。
●Ai AF-I Nikkor ED 300mm F2.8D(IF)(1992)
この代から、ボディ内蔵モータに。現在の超音波モータ搭載のAF-Sレンズの前身。
光学系は新設計となり、最短撮影距離が、3mから2.5mに改善。
ボディ内蔵モータとなったため、AFに対応できるボディは、当時F4以外に、F90やF70と限られていました。
また、この代からDタイプ化(距離エンコーダ内蔵)され、対応ボディでは露出制御精度の向上が期待できます。
AF-SレンズよりAF速度が劣る上に、すでにAF-I用モータの補修部品は払底しているようで、AFモータが故障した場合は修理不可能です。これが怖くて、このレンズは手を出しにくい嫌いがあります。
中古価格はおおむね10万円台半ばから後半。やはりタマ数は少なくなりつつあります。
●Ai AF-S Nikkor ED 300mm F2.8D(IF)(1996)
F5が登場した同時期に発売されたレンズ。当時最新の5点AFと秒8コマ連写に対応すべく、AF駆動に超音波モータを搭載し、高速AFを実現。
鏡胴にAFロックボタンを配するなど、よりAFボディでの使い勝手が向上。
光学系も新設計。
重量は3.1㎏と、歴代サンニッパで最も重い。
ライトグレーの設定あり。
中古価格は20万円台後半から30万円台。この代になると、現在でもAF速度も十分なため、中古市場でも人気があり、タマ数も多めです。
●Ai AF-S Nikkor ED 300mm F2.8D II(IF)(2001)
D1Xが登場し、デジタルカメラがいよいよ本格的になり始めた時期に発売されたレンズ。
最短撮影距離が2.5mから2.2mと短くなったほか、鏡胴にマグネシウム合金を採用し、重量が従来の3.1㎏を大きく下回る2.56㎏へと軽量化された。
光学系は前型と同じ。
引き続きライトグレーの設定あり。
中古価格は30万円台前半。
●AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED(2005)
手振れ補正機構VRと、フレアやゴーストを極限まで抑えるナノクリスタルコートを採用。デジタル一眼レフの普及に伴い、等倍での確認が容易となり、ブレに対する要求がシビアになってきた時代に登場。
この代より絞りリングのないGタイプ化された。
重量は2.87kgと増加した。
中古価格は30万円台半ばから40万円前後。
●AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRII(2010)
VRは4段分の補正が可能なII型となり、より手振れ補正が強力になった。A/M(オート優先オートフォーカス)モードを搭載。光学系は前型と同じ。
重量はやや増えて2.9㎏となった。
新品価格は60万円前後。中古価格は50万円前後。
ここまで見ると分かる通り、ほぼ数年毎に新型に置き換えられているのが分かります。
これに比べると、サンヨンはAF化されたS型、AF-Sが搭載されたDタイプと、たったの2本しかありません。
如何に、サンニッパが時代に合わせて最新技術を詰め込んで、プロやハイアマチュアの要望に応えているかが分かりますね。
現行品は2010年発売で、来年あたり次期モデルが登場してもおかしくないです。
次期モデルは、先ごろ発売されたAF-S NIKKOR 400mm f/2.8E ED VRに習って、恐らく重量の軽減が図られ、電磁絞りを採用するのでは、と推測されます。
電磁絞りが採用されれば、対応ボディはまた制限がかかりますが、実質このレンズのユーザーは古い機種を使わないでしょうから、あまり関係ないかもしれません。
中古で狙うとしたら、やはりVRは欲しいので、AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-EDの良品なら、30万円台後半。とはいえ、高価な買い物には違いないので、お金を貯めてじっくり吟味したいと思います。
2年ぶりの百里基地撮影(D810編) ― 2014年10月03日 23時57分
プライベートが忙しくて、すっかり撮影に行けなかった航空自衛隊百里基地、2年ぶりに行ってきました。
この間に機材も変わり、Nikon D810の導入、Nikon 1 V1の導入と言った具合です。
今回は、Nikon D810による写真。
レンズは、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRIIに、必要に応じて2倍テレコンTC-20EIIを使用。
テレコンは、f/9程度まで絞れば、解像感はあまり損なわれないようです。D800の時は、テレコンとの相性が良くなく、解像感が低下するので使っていませんでしたが、D810はそこまでひどく解像感が低下しません。
これも技術の進歩なのか、D800の時はフォーカスの精度が出ていなかったか。
D810はFX時秒5コマ、DX時秒7コマ(MB-D12と単3電池使用時)と、DXにクロップすれば結構連写が効く上に、D800よりさらにバッファが増えたので、バッファフルまでが長く、結構快適に撮影できます。
AFもD800より食付きが良くなったように思います。
グループエリアAFも使いましたが、これも飛びもの撮影には非常に便利でした。
秋空が映えますね。天気が良くてよかった。
2年ぶりの百里基地撮影(Nikon 1 V1編) ― 2014年10月04日 23時46分
今回は、Nikon 1 V1でどのくらい戦闘機が撮れるかのテストも行いました。
このカメラ、既にV3が出ていて2世代遅れですが、この初代機から、AF追従で毎秒10コマ、AF固定なら毎秒60コマの高速連写が可能ですし、FマウントアダプタFT-1を使用すれば、Fマウントレンズも使えます。しかも、135判換算2.7倍の画角になります。
今回は、1 NIKKOR 30-110mmは使用せず、専らFT-1にAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRIIを、場合によってはテレコンバータTC-20EIIを使用しました。
テレコンを使用しても、純正の組合せなので、きちんとExifにも反映されます。
ただし、TC-20EII使用時は、コントラストがかなり低下する他、晴天下でもAFが迷い、はっきり言って動き物の撮影には使用不可能と言って良いです。ピン精度が出ません。
テレコンを使用しなければ、この組合せでも中央1点ですが、AFはコンティニュアスで結構追従します。
ただ、連写時は、メカニカルシャッターでもエレクトリカルシャッターでも、パラパラ漫画の表示になってしまい、動き物の撮影はもう一歩です。
これは新型のV3では改善されているのかな?
やはり動きモノは一眼レフだな、というのを痛感した次第。
ただ、V3に1 NIKKOR 70-300mmが登場し、この組み合わせによる撮影がかなり評価されているようで、海外でもじわじわ人気になっているようなので、やはり新しい機種は気になります。
百里基地番外編 ― 2014年10月06日 23時51分
あい、飛行機じゃない写真(笑
空自の基地とて、常時何かしら飛んでいるわけではありません。
待ちの間は、各カメラマンは木陰で休んだり、携帯いじったり本を読んだり、色々やっとるんです。
そんな中に撮ったのがこちら。
データ:Nikon 1 V1 + AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII Aモード(f/4.5 1/800)-0.7 RAW現像
ハッキリ言いましょう。ニコワンは、レンズでかなり化けるカメラです。
逆に言うと、キットのズームレンズってそれなりなんですね。
絵的なセンスはともかく、70-200mmとの組合せはなかなかの描写を見せてくれます。ただこのレンズ、あまり寄れないのが欠点です。
データ:Nikon D810 + AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII + TC-20EII Sモード(f/7.1 1/800) 290mm ISO500 RAW現像
飛行機撮りのセッティングのまま撮ったので、テレコン入ってますが、こういう撮影はテレコン足でトリミングしたほうが結果が良いです。
データ:Nikon D810 + AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR Aモード(f/11 1/500)-1.0 17mm ISO64 RAW現像
空はすっかり秋ですね。
山岸一雄製麺所 アリオ川口店 ― 2014年10月07日 23時18分
週末に、いつもイオンじゃつまらんしということで、新規開拓で行ってきた、イトーヨーカドーがくっついたアリオ川口店。
子連れですから、当然お昼はフードコートです。イオンより空いてていいですね(笑
山岸一雄製麺所、あの有名な大勝軒の創業者の名前を冠したお店がありました。当然このお店で注文。
最近はフードコートのお店も馬鹿にできませんから。
特製つけ麺いただきました。
う~ん、ちょっとしょっぱいな。スープは豚骨魚介の出汁よりも先に塩分を強く感じました。
あと、麺はもちもち系の太麺ですが、これは明らかに茹で過ぎかな。何だかブヨブヨした感触で、コシがあまりなかったですね。
アリオ川口自体は、イオンより空いていてよかったので、また来た時は普通のラーメンを試してみたいです。
大勝軒…今たくさん分店していますが、まずいって言われている店のほうが多いですからね。
山岸一雄製麺所は、山岸一雄が総合プロデュースしていて、経営自体をしているわけでないので、実質名前を貸しているだけなんでしょうね。
皇居限定の酒 純米大吟醸 御苑(みその) ― 2014年10月09日 23時37分
今よりロゴの斜体が顕著だった時代のアクセサリ ― 2014年10月10日 23時58分
Niukon スライドコピーアダプタ ES-1 ― 2014年10月11日 23時17分
EPSONから、実に7年ぶりに最上位機種のフラットベッドスキャナ、GT-X980が発売されました。
内容的には、光源のLED化(これは下位機ですでに搭載済み)と、フィルムの平面性を保つアンチニュートンリングのフィルムホルダの採用といったところで、7年前のGT-X970の小改良に留まりそうです。
すでにスキャナの世界では、大きな技術進歩はないのかもしれません。
単体スキャナ自体、もはや複合機に押されてニッチな市場ですからね。
国内メーカーからフィルムスキャナが発売されなくなって久しいですが、現状、フィルムスキャンするとなると、以下の方法となります。
1.海外製のフィルムスキャナ
2.国内メーカーの透過原稿対応フラットベッドスキャナ
3.500万画素程度のCMOSセンサ内蔵の簡易スキャナ
1の海外製フィルムスキャナは、台湾などのメーカーから出ているもので、かつての国産フィルムスキャナと同価格帯のものがあります。
性能は悪くなさそうですが、如何せん、海外メーカーであること、誰でも知っている名の通った大手メーカーではないことから、アフターサポートが心配です。値段が値段だけに、不具合発生時が怖い。簡単に修理できなそうです。
また、ドライバなども、きちんと更新してくれるか。そういうのを考えると、リスクがあります。
2が一番安心かつ安定している、と言えます。
しかし、結構場所をとる上に、構造上スキャン時のフォーカスの問題があります。
それを受けての、今回GT-X980がフィルムホルダを改良してきたわけですが、アンチニュートンリングのアクリル板で挟むことは、アクリル板そのものの傷や埃の付きやすさも考慮しなければなりません。
3は、安物デジカメ+透過照明といった構成で、簡易なので色の補正ができない、フォーカスが甘い、そもそもセンサの性能が悪い、ということで、そもそも選択肢に入らない。
これ以外の方法として、今回取り上げるのが、デジカメによるコピーです。
名付けて、「デジタルデュープ」とでも言いましょうか。
デジカメは現在も日進月歩で進化しています。これをフィルムスキャンに使わない手はない。
何しろ、デジカメですから撮影は一瞬。もっともセッティングに少々時間はかかりますが。
実はこの方法、フィルムカメラ全盛期から行われており、フィルムコピーに用いられています。きちんとそれ専用の道具も発売されていました。等倍以上のマクロ撮影をするためのべローズのアダプタとして、スライドコピーアダプタが市販されていました。
これを最近復活させたのが、PENTAXから発売された「PENTAX FILM DUPLICATOR」です。
PENTAXの商品ですが、構造的にどこのメーカーのカメラでも取り付けられます。
しかしお値段が…10万円超えます。
もちろん、それに見合った剛性のある造りでしょうし、フィルムコピーはわずかな平面性のずれもフォーカスがシビアで許されませんから、しっかりしたものを作る以上、現代ではこの値段になるのは仕方ないかもしれません。
しかし、もっと安くやる方法があります!
これが今回導入した、Nikon ES-1 スライドコピーアダプタです。実売4千円しません。マクロレンズ(Nikonで言うMicro Nikkorレンズ)の先端に取り付けます。
前世紀からゾンビのごとく販売されているこの商品、名前を見ると分かる通り、もともとスライドフィルムをフィルムカメラでコピーするための商品で、簡易的なものですが、そのままデジタルカメラにも使用可能です。
しかも、使用できるカメラは、フィルム一眼レフだけではなく、デジタル一眼レフでも可能。
今や3600万画素を超えるD800やD810があるわけです。フィルムカメラと違い、その場で確認できますし、何度もやり直しが効く。しかも、撮った後はRAW現像もできます。
もちろん、レンズの収差などの問題もありますから、フィルム専用のスキャナやフラットベッドスキャナとはまた違った問題は出てきますが、気軽に素早く撮影できるのは大きなメリットです。
レンズは、最新のAF-Sではなく、こちらも前世紀から発売されている、Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8Dを使用します。こちらも今回、1万円台後半の安価に入手。
もともと、この焦点距離のマクロ(Nikonの言うマイクロ)が欲しかったというのもあります。室内物撮りにちょうど良いですし。
なお、Nikon ES-1は、フィルタ径52mmのレンズに取り付けられるようになっているため、Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8DやAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDはフィルタ径62mmですから、変換アダプタのNikon BR-5が別途必要です。
Nikon以外のカメラやレンズにも取り付け可能です。
フルサイズ機の場合は、55~60mmの等倍撮影可能なマクロレンズ(1/2倍までのレンズは中間リング=エクステンションチューブも使用)、ES-1取付け側フィルタ径が52mmなので、必要に応じてステップダウンリングが必要です。
APS-C機の場合は、Nikonの場合、40mmマクロが対応するようです。
必要に応じて、エクステンションチューブを経由すれば、m4/3でも使えるようです。
ES-1はスライドコピーアダプタ、と称しているように、本来スライドにマウントされたフィルムをコピーするためのもので、スリーブのフィルムの場合、直接は取付られません。いや、挟み込むことは可能ですが、フィルムに傷をつけてしまう可能性があります。
ここは工夫して、フィルムホルダを自作するのも手ですが、ちょうど我が家にはNikonのフィルムスキャナ用ストリップフィルムアダプタFH-3がありますので、今回はそれをそのまま利用します。
作例は次回に。
せっかくですから、Nikon D810 + Nikon ES-1 vs Nikon COOLSCAN IV ED vs EPSON GT-X750という対決なんかもやってみますか。スキャナがかなり旧世代ですが…。
特にCOOLSCAN IV EDは、メーカー修理もできませんので、今回ES-1を買ったのは、これがアウトになった場合予防措置でもあります。
ご近所のお祭り ― 2014年10月12日 23時42分
Nikon ES-1とCOOLSCAN フラットベッドスキャナを比較する ― 2014年10月13日 23時48分
それでは、前回の続き、フィルムスキャンを実際に3つのやり方で比較します。
まず、Nikon D810 + Nikon ES-1(Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D)です。
光源は、スピードライトのNikon SB-900を使用。これをワイヤレス発光させます。
発光量はマニュアルで結果を見ながら調整。レンズの絞りはf/11。
マニュアルフォーカスで、ライブビューでピントを追い込みます。
今回は、ポジフィルム、Fujichrome Velvia(初代のISO50 RVP)を使用、撮影は2000年、北海道はオコタンペ湖の様子です。
カメラはNikon F90Xs、レンズはAi AF Nikkor 35mm f/2.8Dです。
D810 + ES-1は、スキャナに搭載の埃や傷の除去機能"Digital ICE"がないので、埃の除去は慎重に行う必要があります。
今回はエアブローのみ行いましたが、やはりホコリが写真に載ってしまいました。
設定については、ES-1を組み合わせたD810は、ピクチャーコントロールをスタンダード、光源はスピードライトSB-900、ホワイトバランスはフラッシュに固定、ADLはオート、感度はISO64です。なお、D810+ES-1のみ、ブログの掲載データ量の関係上、若干解像度を落としています。
COOLSCAN IVは2900dpi、GT-X750は3200dpi、色の設定はデフォルトのままの設定です。
●Nikon D810 + Nikon ES-1
●Nikon COOLSCAN IV ED
●EPSON GT-X750
まず、解像感については、さすがに画素数が多いD810 + ES-1が光りますが、このフィルムの写真自体が、微妙に手ブレしているのが今回わかったので、大差ないといったところ。
色再現については、D810 + ES-1がもっともフィルムの色に近い印象。COOLSCANもフィルムの色に近いですが、若干くすんだ印象です。
GT-X750は、赤みが薄くなっていて、夕焼けっぽさがないですね。
結果的には甲乙つけがたいですが、手軽に撮れると思っていたD810とES-1の組み合わせ、実際には、傾きを微妙に直したり、マクロ付近での焦点距離の目減りから、フォーカスを動かすたびに、ES-1のフレーミングを変えなければならないなど、意外と面倒で、トータル作業時間はそれほどアドバンテージはないかも。
そうなると、古いながら、色再現性に過ぎれ、ホコリ除去も行えるCOOLSCAN IVはなかなかの性能です。
気が向いたら、モノクロフィルム、カラーリバーサルフィルムでも比較したいと思います。

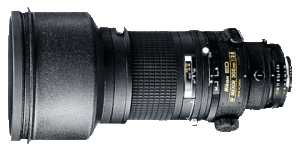






























最近のコメント